
親知らずの抜歯は、麻酔をかけてから行われるため、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。しかし、麻酔が切れた後には痛みを生じる場合があります。
抜歯後の痛みがどれくらい続くのか、どのように対処すれば良いのか不安を抱える方も多いでしょう。
この記事では、親知らず抜歯後の痛みの持続期間や対処法について詳しく解説します。
抜歯後の痛みはいつまで続く?

抜歯後の痛みがいつまで続くかは人それぞれですが、一般的な経過を知っておくと安心できます。ここでは、抜歯後の痛みが続く目安や長引く可能性について解説します。
通常1週間程度で痛みは治まる
親知らずの抜歯後、痛みが続く期間は個人差がありますが、通常は1週間程度で治まることが多いです。
手術中は麻酔が効いているため痛みを感じることはほとんどありませんが、麻酔が切れると傷口から痛みが生じます。
この痛みは通常、抜歯後1〜2日でピークを迎え、その後徐々に和らいでいきます。
一般的には、適切なケアと治療を行えば、1週間以内に痛みは軽減し、日常生活に支障をきたすことなく回復するでしょう。
痛みが長引く可能性
親知らずの抜歯後、痛みが通常の範囲を超えて長引く場合は、早めに医師に相談することが重要です。
以下のような状況の場合は、医師への相談を検討してください。
- 1週間以上痛みが続く
- 痛みが軽減せず、悪化する
- 鎮痛剤が効かない
- 発熱や腫れを伴う
このような症状が見られる場合は、できるだけ早く歯科医院を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
早めに対処することで、合併症を防ぎ、回復の促進が期待できます。
親知らず抜歯後に痛みが生じる理由
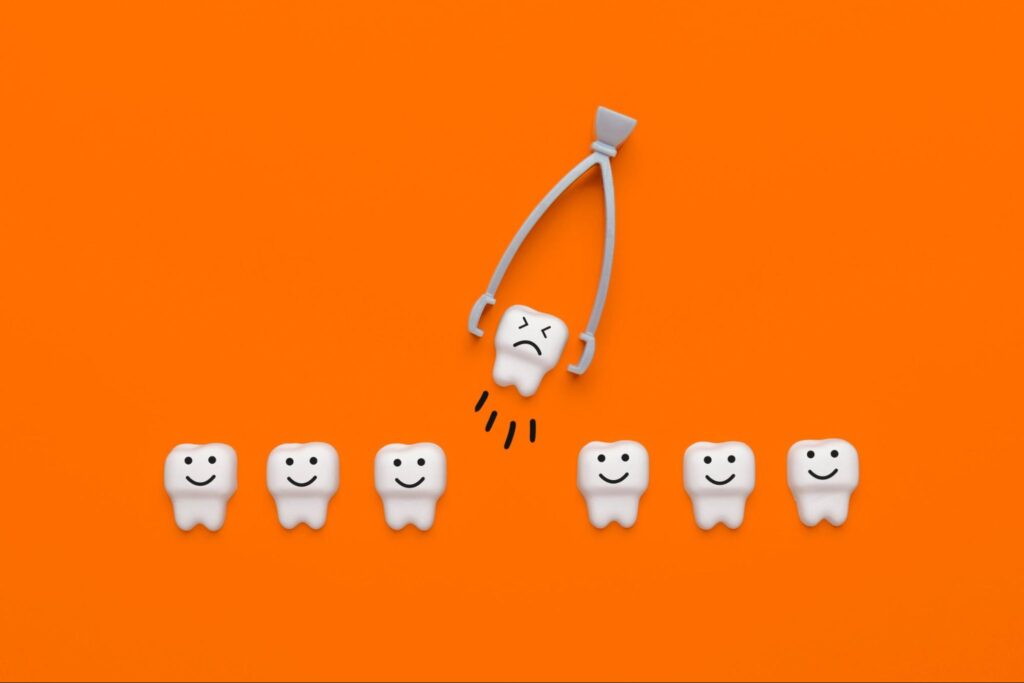
親知らずの抜歯後の痛みは、抜歯という外科的処置によって引き起こされる、さまざまな要因によって発生します。
ここでは、親知らず抜歯後に痛みが生じる主な理由について詳しく解説します。
ドライソケット
抜歯後、通常は傷口に血餅が形成されることで、傷口を保護し、細菌感染を防ぎます。
ドライソケットは、何らかの理由でこの血餅が形成されなかったり、剥がれてしまったりして、骨が露出し痛みを引き起こしてしまう合併症です。
骨が露出した状態は通常の痛みとは異なり、抜歯後2〜3日目から痛みが増し、ズキズキとした激しい痛みが1〜2週間続く場合があります。
ドライソケットは特に下顎の親知らずで起こりやすく、抜歯後の過度なうがいや喫煙、または抜歯部位を触るなどが原因となるケースがあります。
神経への影響
親知らずは顎の奥深くに位置している場合が多く、抜歯時に周囲の神経が刺激されることがあります。
特に下顎の親知らずの場合、重要な下歯槽神経に近接しているため、神経を刺激する可能性が高いです。
下歯槽神経が刺激されると、鋭い痛みやしびれが発生し、一般的な術後の痛みとは異なる神経痛が生じることがあります。
神経が損傷を受けると、痛みは長引く場合があり、通常の鎮痛剤では十分に和らげられないため、専門的な治療が必要となるケースもあります。
筋肉や顎への負担
抜歯は顎に大きな負担をかける手術で、周囲の筋肉が緊張状態になる場合があります。
特に、咬筋や内側翼突筋といった口の開閉に関わる筋肉が緊張すると、痛みや違和感が生じやすいです。さらに、抜歯後の炎症がこれらの筋肉に広がると、痛みが一層強まることもあります。
顎の筋肉が緊張すると、口を開けるのが難しくなったり、噛むときに痛みを感じたりすることがあります。
痛みは通常、時間の経過とともに改善されますが、長引く場合には顎関節症の可能性も考えられます。術後は無理をせず、安静にすることで回復を早めることが重要です。
細菌感染
通常、免疫系が細菌の侵入を防ぎますが、免疫力が低下している場合や適切なケアが行われない場合、抜歯後の傷口は一時的に開いているため、感染リスクが高まります。
特に、処方された抗生物質を正しく服用しないと細菌感染のリスクが増加します。
感染の症状は軽度から重度までさまざまで、炎症や腫れ、痛みの悪化を伴い、細菌感染が進行すると、血液中に細菌が広がり敗血症を引き起こすため、早期の対応が重要です。
抜歯後は口腔内を清潔に保ち、指示された抗生物質をしっかりと服用しましょう。痛みや腫れが1週間以上続いたり、悪化する場合は歯科医師に相談し、適切な治療を受けることが必要です。
痛みを軽減する方法

親知らずの抜歯後に生じる痛みは、適切な対策を講じることで、軽減できます。ここでは、術後の痛みを和らげ、快適な回復を促進するための具体的な方法について詳しく解説します。
医師から処方された薬を正しく使用
親知らずの抜歯後に痛みを軽減するためには、医師から処方された薬を正しく使用することが重要です。痛み止めや抗生物質は、抜歯後の痛みや感染を防ぐために処方されます。
まず、痛み止めは麻酔が切れる前に服用することで、痛みのピークを和らげる効果があります。麻酔が切れるのは通常2〜3時間後なので、その前に服用するのが効果的です。
また、処方された薬は決められた時間に飲むことで、最大限の効果を発揮します。
抗生物質については、細菌感染を防ぐために処方されるものであり、指示された期間中は最後まで服用することが求められます。
途中で服用を中止すると、感染症のリスクが高まるだけでなく、耐性菌の発生につながる可能性もあるため注意しましょう。
さらに、薬を服用しても痛みが改善しない場合や副作用が現れた場合は、すぐに医師に相談することが大切です。
冷却する
親知らずの抜歯後に痛みを軽減するためには冷却が効果的です。術後の腫れや炎症を抑え、痛みを和らげます。
施術部位の冷却は、術後24時間以内に行うと最も効果的です。
例えば、氷嚢や冷却パックをタオルで包み、抜歯した側の頬に15〜20分間隔で当て、その後20〜30分間休むというサイクルを繰り返すことが推奨されます。
冷却によって血管が収縮し、出血や腫れが軽減されるため、痛みの緩和に繋がります。
ただし、直接肌に氷を当てると凍傷のリスクがあるため、必ず布で包んで使用することが重要です。
過度な冷却は逆効果となる場合もあるため、適度な時間と温度で行うことが大切です。
冷却による痛みの軽減は一時的なものですが、適切に行うことで術後の不快感を大幅に和らげることができます。
抜歯後の注意点
親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで痛みを軽減し、回復を促進することができます。以下の注意点を守ることが重要です。
- うがいをしすぎない
- 麻酔が効いている間は食事をしない
- 柔らかい食べ物を選ぶ
- 抜歯箇所に刺激を与えない
- 長時間の運動・入浴を控える
- 飲酒・喫煙を控える
血餅が剥がれると出血が長引く可能性があります。血餅は傷口を保護し、治癒を促進するため、過度なうがいは避けましょう。
麻酔が効いている間は温度感覚が鈍くなっていて、熱い食べ物や飲み物による火傷に気付かないことがあるため、注意が必要です。
指や舌で触れたり、硬い食べ物で圧力をかけたりすると痛みを誘発し、縫合糸が外れて傷が開く恐れがあります。
柔らかい食べ物を選び、治療部位への刺激を少なくするように心掛けましょう。片側の歯で噛むなどして負担を軽減します。
体温を上昇させ、血流を増加させるため、腫脹がひどくなる可能性があるため、術後は安静に過ごすことが推奨されます。
喫煙は創部の粘膜化を遅らせ、痛みが持続する原因となるため、少なくとも抜歯後数日は禁煙することが望ましいです。
以上の注意点を守ることで、抜歯後の不快感を最小限に抑え、スムーズな回復を目指すことができるでしょう。
親知らず抜歯の長期的なメリット
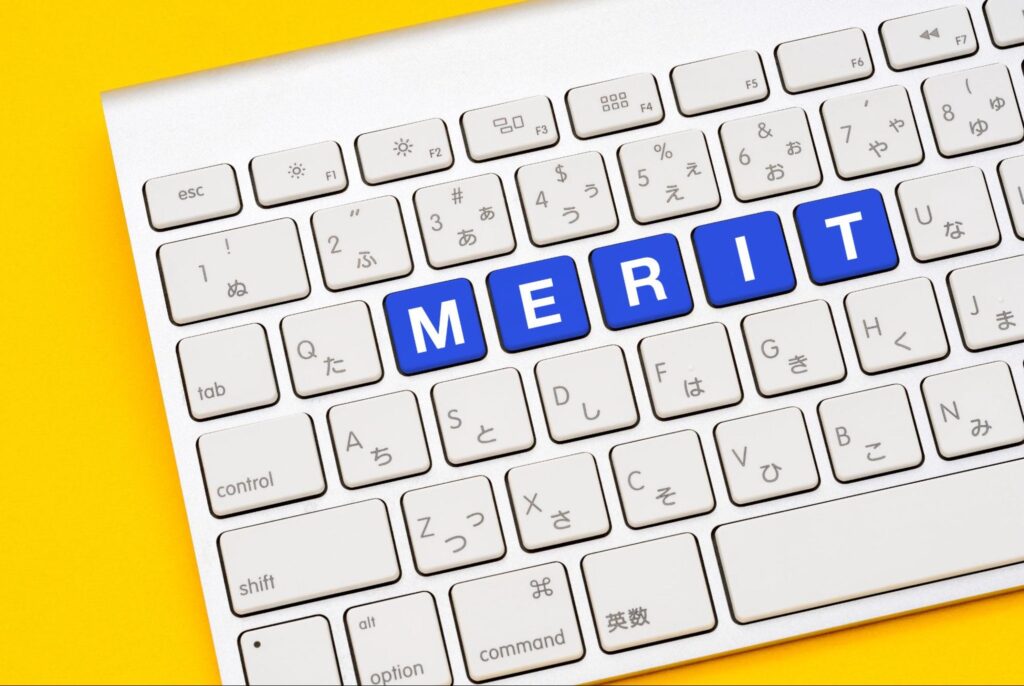
親知らずの抜歯は、短期的な痛みや不快感を伴うことが多いですが、その決断には多くの長期的なメリットが隠されています。
ここでは、親知らずの抜歯がもたらす具体的な長期的メリットについて詳しく解説します。
虫歯や歯周病のリスク軽減
親知らずは口腔内の一番奥に位置し、歯磨きが難しいため、磨き残しが発生しやすいです。
特に親知らずが斜めに生えていたり、一部しか見えていなかったりする場合には、食べ物が詰まりやすくなります。
歯垢や歯石が蓄積しやすくなり、虫歯や歯周病の進行を促進する要因となるため、注意が必要です。
さらに、親知らずは隣接する歯にも悪影響を及ぼすことがあります。例えば、親知らずが正常に生えていない場合、隣の歯を押してしまい、その結果、隣接する歯も虫歯になりやすくなります。
抜歯によって口腔内の清掃が容易になり、健康的な口腔環境を維持することが可能です。
歯並びの維持
親知らずが存在することで、他の歯に圧力をかけ、歯列全体のバランスが崩れることがあります。
特に、親知らずが斜めや横向きに生えている場合は、隣接する歯を押し出し、歯並びが悪化する原因となります。
圧力を取り除くために親知らずを抜歯することで、矯正治療後の理想的な歯並びを安定させることが可能です。
さらに、抜歯によって歯を動かすためのスペースが確保されるため、矯正治療がよりスムーズに進行します。
治療期間の短縮や治療効果の向上も期待できるため、抜歯は矯正計画において重要な選択肢です。
親知らずの抜歯は、単にスペースを作るだけでなく、長期的に美しい歯並びを維持しやすくし、再治療のリスクを低減するためにも有効です。
合併症やリスクの低減
親知らずを放置すると、周囲の組織に様々な影響を及ぼし、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
例えば、親知らずの周囲に嚢胞(のうほう)が形成されること、時間とともに大きくなり、顎の骨を溶かしたり、神経を圧迫したりするケースがあります。
さらに、親知らずが完全に埋まっている場合でも、将来的に感染や炎症を引き起こすリスクが高まるでしょう。
また、親知らずが原因で顎関節症を発症することもあり、これが慢性的な痛みや不快感につながることがあります。
リスクは年齢とともに増加し、抜歯手術の難易度も高くなるため、若いうちに予防的に抜歯することが推奨されます。
早期に抜歯を行うことで、これらの合併症を未然に防ぎ、口腔内の健康を長期的に維持することが可能です。
親知らずの状態や位置によっては、定期的な歯科検診で適切な時期に抜歯を検討することが重要です。
よくある質問と回答

親知らずの抜歯は必要かどうか、術後の痛みやケアについてなど、事前に知っておきたいポイントは多岐にわたります。
ここでは、親知らずの抜歯に関してよく寄せられる質問について、詳しく解説します。
親知らずは必ず抜かなければならない?
必ず抜歯が必要な訳ではありません。
親知らずが痛みや腫れを引き起こしている場合や、他の歯に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、抜歯が推奨されます。
特に、親知らずが斜めに生えていたり、一部だけが歯肉から出ている場合には、周囲の歯や歯茎に問題を引き起こすことがあります。
抜歯の所要時間はどれくらい?
親知らずの抜歯にかかる時間は、親知らずの位置や生え方、抜歯の難易度によって大きく異なります。
一般的に、まっすぐ生えている親知らずの場合、抜歯自体は比較的短時間で済むことが多く、10分から30分程度で完了することが一般的です。
しかし、横向きに生えていたり、骨の中に埋まっている場合は、抜歯の難易度が上がり、30分から60分程度かかることがあります。
特に下顎の親知らずは、骨や神経との位置関係が複雑な場合が多く、より時間を要することがあります。
抜歯前には麻酔を行い、術後には消毒や出血の確認を行うため、全体としては来院から帰宅まで30分から1時間程度を見込んでおくと良いでしょう。
親知らずの抜歯の相場は?
親知らずの抜歯は基本的に保険適用内で行われるため、3割負担の場合、費用はおおよそ1,000円から5,000円程度です。
まっすぐ生えている親知らずの場合は比較的安価で、1,000円から1,500円程度となることが多いです。
一方、横向きに生えていたり骨に埋まっている場合は、手術が複雑になるため、1,500円から5,000円程度の費用がかかります。
親知らずの抜歯は妊娠中でもできる?
妊娠中の親知らずの抜歯は可能ですが、慎重な判断が必要です。
一般的に、妊娠初期(1〜4ヶ月)は胎児の器官形成が進む重要な時期であり、麻酔や薬物の影響を避けるため、抜歯は避けられることが多いです。
妊娠中期(5〜8ヶ月)は「安定期」と呼ばれ、母体の状態が比較的安定しているため、抜歯が可能とされています。
安定期には局所麻酔を使用して処置を行えますが、妊娠高血圧症や貧血などの合併症がある場合は、抜歯を控えることが推奨されます。
妊娠後期(8ヶ月以降)は、体調の変化やお腹の大きさから仰臥位性低血圧症を起こすリスクがあるため、抜歯は避けた方が良いです。
いずれの場合も、産婦人科医と歯科医師との連携を図り、母体と胎児の健康を最優先に考えた上で判断することが重要です。
まとめ
親知らずの抜歯後の痛みは通常1週間程度で治まりますが、個人差があります。
痛みを軽減するためには、医師から処方された薬を正しく使用し、冷却や適切なケアを行うことが重要です。痛みが長引く場合は、早めに歯科医師に相談することが推奨されます。
下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、個室での診療や厳格な滅菌体制により、清潔で安全な環境を整えています。
お子様連れでも安心して通院できるよう、保育士が常駐するキッズルームも完備しています。
親知らず抜歯をご検討の方は、ぜひ下高井戸パール歯科クリニック・世田谷にご相談ください。
#親知らず #親知らず抜歯 #親知らず痛み



