
親知らずを抜歯したいけれど、費用がいくらかかるかわからず不安という方も多いと思います。
この記事では、親知らずの抜歯にかかる費用、抜いたほうがいい親知らずの判断基準、治療方法について詳しく解説しています。
親知らずの抜歯費用が心配な方、親知らずを抜くか迷っている方、どんな治療をするのか不安な方は、ぜひ記事をご覧ください。
親知らずの抜歯にかかる費用

親知らずの抜歯にかかる費用は、親知らずが生えている向きや抜歯する本数によって変わります。
また、保険診療か自由診療かによっても費用が変わってきます。
以下は、主に症状がある場合に適用される保険診療の場合の一般的な費用を解説しています。
保険診療になるのは、腫れや痛みがある、虫歯や歯周病になっている、親知らずが周囲の歯を圧迫しているなどのケースです。また、将来的に重篤な病気になる恐れがある場合も適用されることがあります。
保険診療になるかどうかは、歯科医院に相談してみましょう。
親知らずの生え方によって費用は変わる
親知らずは、生え方に個人差があります。
特に、現代人は顎が小さくなっているため、親知らずが生えるスペースが確保できず、横向きや斜めに生えてくるケースも多いです。
生える向きが正常でない場合には、抜歯の難易度や方法が変わってくるため、費用が多くかかるケースが一般的です。
まっすぐ生えている場合
親知らずがまっすぐ生えていて、完全に露出している場合の抜歯費用は、麻酔代や投薬代も含め2,000円程度です。
通常の抜歯と変わらず治療時間は10分程度とされています。
複雑な生え方をしている場合
親知らずが横向きや斜めに生えている場合には、まっすぐ生えている場合に比べて費用が高くなる傾向にあります。
親知らずが横向きや斜めに生えている場合の費用は、麻酔代も含めて4,000円程度かかるのが一般的です。
また、親知らずが完全に埋没している場合はさらに難易度が上がるため、治療時間も費用も増え、6,000円前後となります。
2本同時に抜歯する場合
親知らずを2本同時に抜歯する場合の費用は、検査費用や投薬代などを含めて4,000円から12,000円です。
1本だけを抜歯するよりも、レントゲン撮影などの検査費用や投薬代が一回で済むため、費用面ではメリットがあります。
4本同時に抜歯する場合
親知らずを4本同時に抜歯することも可能なケースがあります。
通院時間を減らしたい、痛みを一回で終わらせたいと考えている方は4本同時の抜歯を検討する方もいるでしょう。
親知らずの4本同時抜歯にかかる費用は、8,000円から20,000円程度です。
4本同時の抜歯が難しいケースもあり、可能かどうかは歯科医師が診察のうえ判断します。
抜歯以外で追加でかかる費用
親知らずの抜歯以外に追加でかかる費用は以下の通りです。
- 検査費用(レントゲン撮影など)
- 歯のクリーニング代
- 紹介状代
検査費用
親知らずの抜歯にはレントゲン撮影などの検査が必要となります。
一般的な検査費用は3,000円程度です。
完全に埋まっている親知らずを抜く場合には、CTスキャンによる詳細な検査が必要となり、4,000円程度となります。
歯のクリーニング代
親知らずの虫歯や口腔内に炎症がある場合は、抜歯の前にクリーニングを行い、炎症を抑える必要があります。
クリーニング費用は1,000~1,500円程度かかります。
紹介状代
高難易度の抜歯になるケースでは、大学病院での抜歯となる場合もあります。
その場合、歯科医院から大学病院への紹介状代が5,000円程度かかります。
自由診療で行う親知らずの抜歯費用

親知らずの抜歯費用は、保険診療と自由診療で大きく変わります。
保険診療が適用されない親知らずの抜歯は以下のような場合です。
- 予防的な抜歯
- 歯列矯正のための抜歯
- 全身麻酔や点滴麻酔(静脈内鎮静法)を利用する場合
症状がなく、将来的な不安があり抜歯を希望する場合、受け口や歯並びなどを矯正するために抜歯が必要な場合には自由診療となります。
まっすぐに生えている親知らずであれば1本5,000円程度、横向きや斜めに生えている場合は1本10,000円程度、完全埋伏の場合は1本15,000円程度の費用がかかります。
また、抜歯する際に点滴麻酔(静脈内鎮静法)や全身麻酔を使用したほうがよいと判断された場合や希望をする場合にはさらに費用がかかります。
自由診療の場合は麻酔代が高くなる傾向にあり、歯科医院によって異なりますが20,000〜100,000円程度の費用がかかります。
親知らずの抜歯費用を抑える方法

親知らずの抜歯費用を少しでも抑えたい、という方も多いでしょう。
抜歯費用を抑える制度として、以下の2つを紹介します。
- 医療費控除
- 高額療養費制度
それぞれの制度について、詳しく解説していきます。
医療費控除
医療費控除とは、家族の分も含めて、1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、申請することで税金の一部が還付される制度です。
抜歯にかかった費用だけでなく、他の診療費にかかった費用も合算できますし、生計をともにする家族がいる場合にはその家族の医療費も合算できます。
医療費控除を利用することで、経済的な負担を抑えられるでしょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、その月に支払った自己負担分の医療費が、自己負担限度額を超えた場合に後で払い戻せる制度です。
自己負担額は生計をともにする家族がいる場合、その家族の分も合算できます。
限度額については、年齢や所得によって設定されており、加入している健康保険組合に申請することで、超えた場合の払い戻しを行えます。
詳しくは、加入している健康保険組合、全国健康保険協会のホームページなどでご確認ください。
親知らずは抜いたほうがよい?

親知らずの抜歯には費用がかかるため、親知らずの抜歯をしたほうがいいのか、と悩む方も多いでしょう。
ここでは、抜いたほうがよい親知らずと抜かなくてもよい親知らずの判断方法について解説します。
抜いたほうがよい親知らず
抜いたほうがよいと判断される親知らずは以下の4つのケースです。
- 親知らずが横向きや斜めに生えている場合
- 噛み合わせが合わなくなっている場合
- 親知らずが虫歯や炎症になっている場合
- 親知らずが原因で炎症が起こっている場合
親知らずが横向きや斜めに生えている場合
親知らずが横向きや斜めに生えていると、親知らず自体や隣の歯との隙間に歯ブラシがうまく届かず汚れが溜まり、虫歯や歯周病の原因となります。
また、横や斜めに生えてくる親知らずは隣の歯を圧迫し、痛みを伴う、歯並びが悪くなるなどの影響も出てくる場合があります。
噛み合わせが合わなくなっている場合
親知らずが原因で噛み合わせが合わなくなる場合は多く見られます。
噛み合わせが合わなくなることで、咀嚼時の左右の顎のバランスが崩れ、顎関節症を引き起こすこともあります。
また、頭痛の原因となることもあり、噛み合わせが合わなくなっている場合は親知らずの抜歯が検討されます。
親知らずが虫歯や炎症になっている場合
親知らずに虫歯や炎症が起こっている場合、ほとんどのケースで抜歯が勧められます。
親知らずは磨きにくく虫歯や炎症が起こりやすい歯であり、治療しても再発してしまう可能性が高いためです。
虫歯や炎症が進行・再発すると隣の歯にも悪影響を及ぼしかねないため、将来的なリスクや負担を抑えるためにも抜歯を検討しましょう。
親知らずが原因で炎症が起こっている場合
親知らずが原因で引き起こされる口腔内の炎症を智歯周囲炎といいます。
親知らずが生え、歯ブラシが届かないと汚れが溜まっていき、細菌が増殖していきます。
その細菌が口腔内に広がると炎症が起こり、歯肉の痛みや腫れ、膿が出る、発熱するなどの症状が出てしまうことがあります。
一度炎症を起こすと再発することが多いため、抜歯を勧められるケースもあります。
抜かなくてもよい親知らず
まっすぐに生えている親知らずで、腫れや痛みなどの症状が出ていない、噛み合わせに問題のないケースでは抜歯をする必要はないと判断されることが多いでしょう。
また、完全に埋没していて症状が出ていない場合も、抜歯を行わずに済むことが多いです。
歯科医院での相談をして、適切な処置ができるようにしましょう。
親知らずの治療の流れ

ここでは、親知らずを抜歯する流れについて紹介します。
1:問診・診察
まずは、歯科医院での問診・診察です。親知らずにどのような症状が出ているか、患者さんから話を聞き、歯科医師が状態を確認します。
親知らずのことで疑問に感じることや希望がある場合には、事前に歯科医師に話しておきましょう。
2:レントゲン撮影
親知らずは半分だけ埋まっている場合も多く、見た目では歯肉の中でどのように生えているのかわからないこともあります。
レントゲン撮影をすることで歯の状態を詳しく知ることができます。
レントゲン撮影でわからない場合では、さらに詳細なCT検査を行うこともあります。
撮影した画像を見ながら、歯科医師が診療計画を立てていきます。
3:抗生物質の処方
口腔内に炎症がある場合には、抜歯よりも先に炎症を治さなければなりません。
炎症している箇所のクリーニング、抗生物質の直接投与の治療を行い、自宅でも数日間抗生物質を服用して細菌の繁殖を防ぎます。
4:麻酔
炎症の治療が終わった後には、親知らずの抜歯を行います。
親知らずは、1本や2本の抜歯には局所麻酔を使用しますが、4本同時抜歯の場合には、点滴麻酔や全身麻酔を使用することが一般的です。
5:抜歯
親知らずは、抜歯鉗子(ばっしかんし)と呼ばれるペンチのような器具を使って抜歯します。
まっすぐ生えている場合は、通常の抜歯と変わらず、引き抜くだけで抜歯できる場合がほとんどです。
斜めや横向きに生えていたり、埋没している場合には、歯肉の切開や歯の分割が行われます。
抜歯の方法は生えている歯の状態でも変わってくるため、歯科医院のカウンセリング時に詳細を聞くことで不安が解消されるでしょう。
6:止血と縫合
抜歯した箇所の汚れを取り除いたら止血し、縫合を行います。
抗生剤や止血剤を直接塗布する、ゼラチンスポンジで止血するなどの処置を行い、糸で縫合していきます。
抗生剤は自宅でも服用するために処方されますので、用法用量を守って服用してください。
親知らずの抜歯後は痛みや腫れが出ることがありますが、長くとも1週間程度で治まることがほとんどです。
1週間以上経っても痛みや腫れが続く場合は、抜歯した歯科医院に相談しましょう。
7:抜糸
数日から一週間後に抜糸が行われ、問題がなければ親知らずの抜歯治療は完了です。
親知らずを放置するリスク
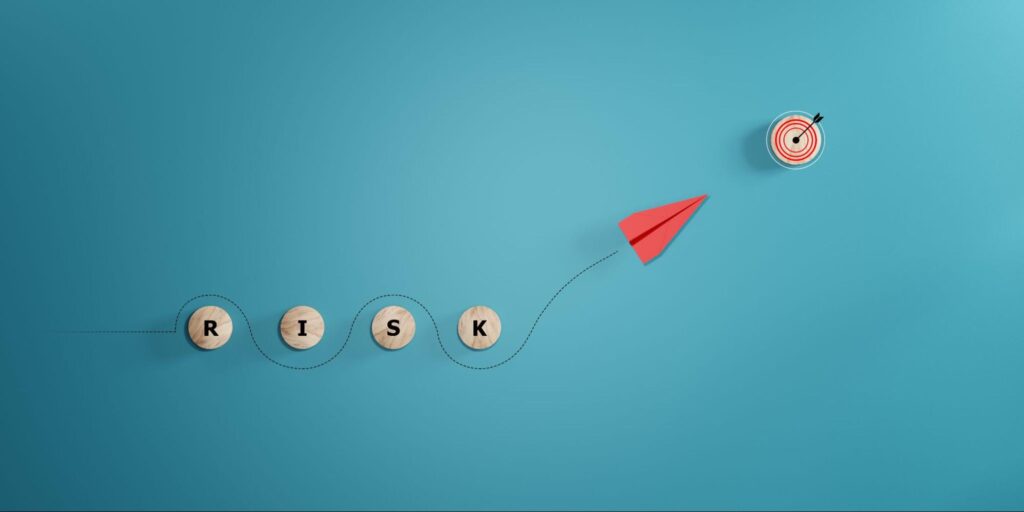
親知らずを放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 痛み・腫れが出る場合がある
- 虫歯や歯周病のリスク
- 周囲の歯に炎症が起こる
- 歯並びや噛み合わせが悪くなる
痛み・腫れが出る場合がある
親知らずは磨きにくく汚れが溜まりやすい歯で、虫歯菌や歯周病菌など細菌の温床になりやすいため、歯肉の腫れや痛みが出やすくなります。
また、親知らずが隣の歯を圧迫することでも痛みが出ることがあります。
親知らずの痛みがいつ起こるかは予測できません。夜間や旅行中などにも現れることがあり、つらい症状を我慢しなければならない場合もあるでしょう。
虫歯や歯周病のリスク
親知らずは通常のブラッシング方法では歯ブラシが届きにくく、気づかないうちに食べかすなどの汚れが溜まっていることもあります。
汚れを放置してしまうと、細菌が増殖していきます。
不規則な生活、ストレス、寝不足、バランスの悪い食事などで体の抵抗力が弱っていると、さらに細菌が増えてしまい、親知らずだけでなく他の歯の虫歯や歯周病リスクを高めます。
周囲の歯に炎症が起こる
親知らずは智歯と呼ばれ、親知らずが原因の口腔内の炎症を智歯周囲炎と呼びます。
智歯周囲炎は細菌が親知らずの周りに増殖し、炎症を引き起こしている状態です。
智歯周囲炎になってしまうと、口腔内の痛みや腫れだけでなく、顎や顔までが腫れたり、発熱することもあります。
歯並びや噛み合わせが悪くなる
親知らずが生えていることにより、歯並びや噛み合わせが悪くなることがあります。
噛み合わせが悪くなることで、虫歯や歯周病になりやすくなる、顎関節症になる、頭痛、肩こりなど、さまざまな悪影響が引き起こされます。
まとめ
親知らずの抜歯にかかる費用は、親知らずの生えてくる向きや本数によって変わります。
また、保険診療か自由診療かによっても大きく変わってくるため、歯科医院に相談して、自分の親知らずの抜歯にかかる費用や必要な処置について聞いてみましょう。
下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、しっかりと事前の検査診断を行い、難症例の場合は日本口腔外科専門医が担当します。
親知らずを抜歯するメリットやデメリットについても、患者さんの状況に応じて歯科医師が詳しく相談に乗ります。
親知らずの抜歯の費用が気になっている方は、ぜひ下高井戸パール歯科クリニック・世田谷にご相談ください。
#親知らず #親知らず抜歯費用



