
親知らずが痛んだり、違和感があったりして「今日親知らずを抜きたい」と思うこともあるかもしれません。
親知らずの当日抜歯は可能なのか、できないケースはどういったものなのか知っておきたい方もいるでしょう。
この記事では、親知らずの当日抜歯は可能なのか、難しいケースやリスク、抜歯後の注意点などを解説します。
親知らずの当日抜歯を希望している方、当日抜歯のリスクを知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
親知らずの当日抜歯は可能?

親知らずの当日抜歯は状況によっては可能です。
正確には、抜歯予定の親知らずが上側なのか、下側なのかによって可能かどうかが異なります。
上顎の親知らずであれば、当日抜歯が可能なことが多いです。
上側の親知らずは真っすぐに生えてくることが多く、通常の抜歯と難易度がさほど変わらないため当日抜歯ができるかもしれません。
実際に「上側の親知らずであれば当日抜歯可能」としている歯科医院もあります。
一方で、下側の親知らずは当日抜歯が難しいことが多いです。
下側の親知らずは上側と比べて横や斜めを向いて生えていることが多いため、通常の抜歯と比べて難易度が高く時間がかかるためです。
また、下側は顎の神経が近くにあるため、神経を損傷させないように治療を進める必要があります。
基本的には後日抜歯することが多い
親知らずの生え方によっては当日抜歯可能な歯科医院もありますが、基本的には後日抜歯することが多いです。
後日抜歯の理由は抜歯によるリスクをできるだけ軽減させるためで、他に歯科治療を受けていれば、そちらの治療状態の兼ね合いもあります。
また、抜歯難易度が高い場合は大学病院やより設備の整った歯科医院などを紹介されることもあります。
親知らずの当日抜歯が難しいケース
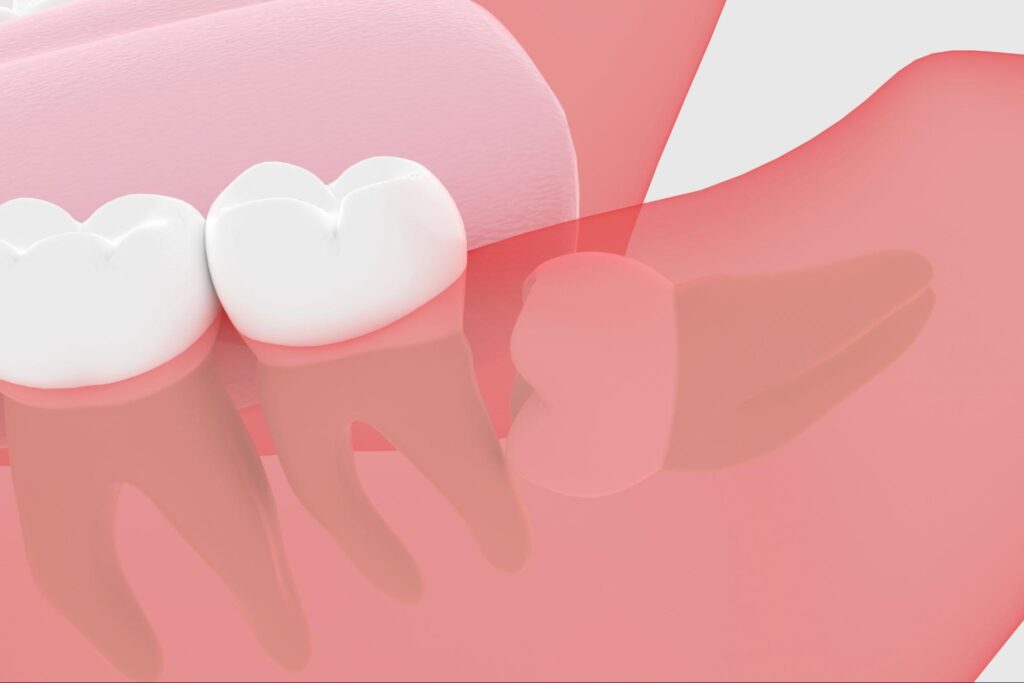
親知らずの当日抜歯が難しいケースはさまざまです。
ここでは、当日抜歯を断られることの多い5つのケースを解説します。
腫れや痛みなどの炎症がひどい
腫れや痛みなどの炎症が起きている場合は当日抜歯を断られることが多いです。
炎症が起きていると麻酔が効きづらく、抜歯後に炎症が悪化したり化膿したりするリスクが高いためです。
どうしても必要な場合に限り、炎症が起きていても抜歯することもあります。
しかし、治療中は激痛が走り、抜歯後も治療が必要になることが多いため、おすすめしません。
炎症が起きている場合、まずは抗生物質の使用やクリーニングなどを行い、炎症を抑えてから抜歯を行います。
予約時間を超過する可能性がある
歯科医院は完全予約制を採用していることが多く、予約時間を超過する可能性がある抜歯はあとの患者さんに迷惑がかかるため断られることが多いです。
親知らずの抜歯前には必ずレントゲンやCTを撮り、親知らず生え方や周辺の血管の場所などを確認します。
- 親知らずのほとんどの部分が骨の中にある
- 根っこが複雑な形になっている・絡まっている
- 炎症により歯が溶けている
- 顎の骨とくっついている など
上記のような状態の親知らずであれば、抜歯に時間がかかる可能性が高いです。
体調が悪い
抜歯当日に体調が悪い場合は抜歯の延長を提案されることが多いです。
体調や気分が悪い時に麻酔を使用すると脳貧血を起こしたり、免疫力が低下しているため抜歯後の感染症リスクが高まったりします。
真っすぐに生えている親知らずの抜歯でも、身体には負担がかかります。抜歯は体調が万全の状態で行うようにしましょう。
1週間以内に大切な予定がある
抜歯後1週間以内に大切な予定がある場合、抜歯を断られることが多いです。
抜歯後は2〜3日をピークに腫れや痛みなどの症状が現れ、1週間程度で治まります。
この1週間は食事内容や激しい運動などに注意して過ごす必要があります。
そのため、結婚式やお出かけなど大切な予定がある場合はそれらの予定が終わってからの抜歯がおすすめです。
全身状態を確認したうえで難しい
親知らずの状態としては当日抜歯が可能でも、高血圧や糖尿病、血液に関する服薬をしている場合など全身状態によっては当日抜歯はできません。
主治医と連絡を取り抜歯をしても問題はないか確認を取ったり、お薬手帳や実際の薬の確認を行ったりするため、当日抜歯は難しいです。
主治医とも抜歯を行っても問題がないと判断ができてから抜歯方法や日程を決めることになります。
親知らずを当日抜歯するリスク

親知らずの当日抜歯にはさまざまなリスクが存在します。
ここでは、当日抜歯のリスクを解説します。
精密検査ができない
親知らずの生え方や根っこの状態は個人差があり、必ずレントゲンやCTなどの精密検査を行ったうえで抜歯計画を立てます。
しかし、当日抜歯であれば予約時間の制限もあるため、精密検査を十分に行うことが難しく痛みに最大限配慮した治療が行えないかもしれません。
また、治療を始めてから想定外が起きる可能性もあります。
できるだけ想定外を減らすためにも当日抜歯は避けるのがおすすめです。
炎症がさらに悪化する可能性がある
軽度でも炎症が起きている状態で抜歯するとさらに悪化する可能性があります。
親知らずが原因の炎症が悪化すると、智歯周囲炎や頬部蜂窩織炎などの疾患になり、輪郭が変わるほど腫れたり高熱が出たりする可能性もゼロではありません。
炎症の可能性があれば、親知らずの抜歯は避けるようにしましょう。
親知らずの抜歯に関する費用相場

基本的に親知らずの抜歯は保険診療が可能ですが、矯正治療や移植を目的とした抜歯は自由診療になります。
また、親知らずがどのように生えているのかによって治療時間が異なるため、費用面も異なります。
親知らずの抜歯に関する1本当たりの費用相場(保険診療)は以下のとおりです。
- 真っすぐ生えている場合:1,000~2,000円
- 斜め・横に生えている場合:4,000~5,000円
基本的に抜歯費用には、初診料・レントゲンやCTなどの検査料・麻酔代が含まれています。
しかし、場合によっては追加費用がかかることもあるため、あわせて知っておきましょう。
抜歯以外の費用
抜歯以外にかかる費用は、主に以下の3つです。
- 抗生剤や痛み止めなどの投薬代
- 紹介状の費用
- 追加麻酔代 など
親知らずの抜歯後は、感染症リスクを下げるため抗生剤や痛み止めを処方してもらえることがあり、その分の費用が必要です。
1,500円前後になることが多く、痛み止めは希望しなければ処方してもらえない可能性があるため、必要であれば必ず伝えましょう。
受診した歯科医院での抜歯が難しい場合、大学病院やより設備が整った病院への紹介状を提供されることがあります。
大きな病院であれば、紹介状がなければ受診できないケースも多く、1通3,000円前後です。
最後に、追加麻酔を希望する場合は別途費用が掛かります。
親知らずの抜歯に必要な麻酔は抜歯費用に含まれていることが多いですが、笑気麻酔を希望する場合は追加費用が必要です。
入院が必要な場合
親知らずの抜歯は基本的に当日で終わりますが、以下に当てはまる場合は入院が必要になる可能性があります。
- 親知らずが深く埋まっている
- 複数同時に抜歯する
- 持病がある
- 呼吸器異常や血管系の疾患がある など
入院して親知らずを抜歯する場合、多くは1泊2日の入院になりますが、症状によっては2泊3日になることもあります。
入院する場合の費用目安は1泊2日で2万〜3万円、2泊3日で6万〜 7万円程度です。
親知らず抜歯当日の流れ

ここでは一般的な親知らず抜歯の当日の流れを解説します。
場合によっては数日かかったり、追加の項目があったりすることもあります。
実際の流れについては、担当医と相談しましょう。
問診やカウンセリング
まずは、問診票を記入したり、どこの親知らずを抜歯したいのかなどカウンセリングを行います。
もし持病があったり服用中の薬があればこの時に必ず伝えておきましょう。
薬に関してはお薬手帳を見せたり、実際の薬を見せるのがおすすめです。
レントゲンやCTを撮る
レントゲンやCTを撮り、親知らずの状態や周辺の血管の場所などを確認します。
ここで撮影したレントゲンやCTを参考にして、今日抜歯ができるのか、どういった治療計画で抜歯を行うのかが決まります。
このタイミングで「今日の抜歯は難しい」と判断されるかもしれません。
また、口腔内の状態によっては歯周病検査も行うことがあります。
抜歯に対するリスクや抜歯後の注意事項などを説明
検査を行い、特に問題がなく抜歯を行う場合は治療計画や抜歯するリスク、注意事項などの説明をうけます。
一通りリスクや注意事項を聞いても、問題がなければ同意書にサインをして抜歯を行います。
麻酔
抜歯前に、表面麻酔や局所麻酔を行います。痛みを感じる場合は、途中で麻酔の追加も可能です。
治療や痛みに対して不安が大きい場合は、笑気麻酔や静脈内鎮静法を取り入れることもできるため相談してみましょう。
抜歯
麻酔が十分に効いていることを確認し、親知らずを抜歯していきます。
身体への負担をできるだけ抑えるため、迅速に抜歯が進められます。
切開が必要であれば、抜歯後に縫合処置が行われることもあり、治療時間は15〜60分程度です。
止血
抜歯後は、止血のために20分程度はガーゼを噛んで過ごします。
特に問題がなければ、ガーゼを噛んだまま自宅に帰ることもあります。
麻酔が効いている間の飲食は避け、抗生剤や痛み止めを処方された場合は医師の指示どおりに服用しましょう。
1週間後に消毒
抜歯1週間後に消毒や経過観察のために来院をお願いされることがあります。
縫合処置をしていれば、このタイミングで抜糸を行います。
抜歯箇所周辺は適切な歯磨きが難しいため、クリーニングもあわせて行われることもあるでしょう。
抜歯後の注意点

最後に、抜歯後の注意点について解説します。
化膿や炎症を起こさないためにも、抜歯後1週間程度は意識して過ごしましょう。
ガーゼを噛んでしっかりと止血する
個人差がありますが、出血が止まるまでに30分程度はかかるため、ガーゼをしっかりと噛み、止血をおこないましょう。
30分ほどである程度出血は止まりますが、数時間は唾液に血が混じることがあります。
気になるかもしれませんが、頻繁にうがいをしたり唾を吐いたりすると逆に出血が止まりにくくなることがあるため、避けましょう。
数日は血行が良くなる行動は控える
抜歯後最低2〜3日(痛みや腫れがある程度落ち着くまで)は血行が良くなる行為は控えましょう。
例えば、長時間の入浴・激しい運動・飲酒などです。
血行が良くなる行為は痛みや腫れを増長させたり、再出血したりすることがあります。
飲食は麻酔が切れてから
抜歯後2〜3時間は麻酔が効いている状態です。飲食は麻酔が切れてからにしましょう。
麻酔が効いている状態で食事をすると、舌を噛んだり火傷や凍傷になったりする可能性があります。
また、抜歯箇所の痛みもないため、食べ物が詰まってしまっても気付けないかもしれません。
抜歯箇所に刺激を与えてしまうと、再出血や血餅が剥がれるドライソケットになることもあるため、できるだけ避けるようにしましょう。
処方された薬は指示どおりに服用する
抜歯を行った際には抗生剤や痛み止めを処方されることがありますが、必ず医師の指示通りに服用しましょう。
抗生剤は感染症の原因になる細菌を抑える効果があり、抜歯後の腫れや細菌感染のリスクを軽減させます。
痛み止めは麻酔が切れたあとの痛みを抑えるためのもので、痛みがなければ服用する必要はありません。
ただし、抗生剤に関しては処方された分はきちんと飲み切るようにしましょう。
内出血が起きたら様子を見る
親知らずを抜歯すると頬や口腔内に内出血を起こすことがあります。
抜歯後1〜2日が経過したタイミングで、頬か口腔内が青黒く内出血を起こすと驚くかもしれませんが、1〜2週間程度で治まる場合は問題ありません。
特に、親知らずが骨に埋もれており、歯茎を切開したり剥がしたりした場合に内出血は起きやすいです。
もし、内出血が悪化したり2週間を超えても治らない場合は歯科医院に相談しましょう。
まとめ
親知らずの当日抜歯は状況によっては可能です。
しかし、親知らずの生え方や炎症の有無、全身状態を加味して当日抜歯が難しいと判断されることもあります。
当日抜歯を希望したいこともあるかもしれませんが、実際に可能かどうかは歯科医師としっかり相談して決めるようにしましょう。
下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、痛みを抑えた・歯を削ることの少ない・神経を残す治療を目指しています。
日本口腔外科専門医が在籍しているため、「親知らずを抜歯したいけど怖い」「なるべく痛みを抑えて治療したい」という方はぜひ一度下高井戸パール歯科クリニック・世田谷にご相談ください。
#親知らず #親知らず当日抜歯



