
入れ歯を作製する際、「費用が高額にならないか」と心配している方もいるのではないでしょうか。
特に、より快適で見た目も自然な入れ歯を求めると、保険適用外の自費診療となり、費用負担が大きくなる傾向があります。
しかし、医療費控除という制度を活用すれば、経済的な負担を軽減できることをご存知でしょうか。
この制度を活用することで、支払った税金の一部が還付される可能性があります。
この記事では、入れ歯治療における医療費控除の基本的な仕組みから、対象となる入れ歯の種類、申請に必要な手続きまで解説します。
入れ歯治療における医療費控除の基本知識

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に税金の負担を軽くできる制度です。
入れ歯の治療も、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
ここでは、入れ歯治療で医療費控除を考える上で、最初に押さえておきたい基本知識を紹介します。
医療費控除制度の仕組みと年間10万円の基準
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、原則として10万円を超えた場合に申請の対象となります。
ただし、年間の総所得金額が200万円未満の方の場合は、10万円ではなく『総所得金額の5%』を超えた金額が基準です。
この控除を受けると、所得税の計算のもとになる課税所得金額が低くなるため、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。
医療費控除は年末調整では手続きできないため、会社員の方であっても、ご自身で確定申告を行う必要があります。
入れ歯が医療費控除対象となる理由と条件
入れ歯治療は、『噛む』『話す』といった口の機能を取り戻すための医療行為とされるため、医療費控除の対象になります。
失われた歯の機能を補うための治療は、病気の治療の一環として扱われるのです。
ただし、すべての歯科治療が対象になるわけではありません。
医療費控除が認められるのは、あくまで機能回復を目的とした治療に限られます。
後述で、医療費控除の対象になる具体的な入れ歯の種類を紹介します。
(参考:国税庁『医療費控除の対象となる医療費』)
入れ歯治療で活用できる補助金制度と高額療養費の仕組み

入れ歯治療の費用負担を軽減する方法は、医療費控除だけではありません。
公的な制度として高額療養費制度や、自治体によっては独自の補助金制度が設けられている場合があります。
まずは、医療費控除と高額療養費制度の違いを簡単に比較してみましょう。
| 医療費控除 | 高額療養費制度 | |
| 対象 | 機能回復目的の医療費(保険・自費問わず) | 保険診療の自己負担分 |
| 手続き方法 | 確定申告で申請 | 健康保険組合に申請 |
| 控除・補助の内容 | 支払医療費ー10万円=所得控除(総所得金額が200万円未満は、総所得金額×5%) | 上限を超えた自己負担分が払い戻される |
| 対象外となる治療 | 審美目的の治療 | 自費診療 |
| 併用の可否 | 高額療養費の払い戻し分を控除計算から差し引く必要あり | 併用可 |
以下に自治体独自の補助金制度や高額療養費制度の詳細を紹介します。
自治体独自の入れ歯治療補助金制度の種類と申請条件
お住まいの自治体によっては、高齢者などを対象に入れ歯の作製や修理に関する独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。
これらの制度は、自治体が主体となって運営しているため、対象者、補助内容、申請条件などは地域によってさまざまです。
利用を検討される場合は、お住まいの市区町村の役所の福祉課や保健センターなどの担当窓口に直接問い合わせて、確認することをおすすめします。
高額療養費制度による入れ歯治療費の自己負担軽減効果
高額療養費制度は、1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
この上限額は、年齢や所得水準によって異なります。
また、高額療養費制度の対象となるのは、保険適用の治療のみです。
そのため、保険で作製する入れ歯については適用される可能性がありますが、全額自己負担となる自費診療の入れ歯は対象外です。
医療費控除と高額療養費の併用
医療費控除と高額療養費制度は併用することが可能です。
ただし、計算方法には注意が必要です。
医療費控除を申請する際には、1年間に支払った医療費の総額から、高額療養費として払い戻された金額を差し引く必要があります。
例えば、年間の医療費が30万円で、高額療養費として5万円が払い戻された場合、医療費控除の計算対象となる金額は25万円となります。
この金額から10万円(または所得の5%)を引いた額が、最終的な控除額です。
申請の順番は、先に高額療養費の申請を行い、支給額が確定した後に医療費控除の確定申告をするのが一般的な流れです。
医療費控除の対象になる入れ歯の種類と治療内容

入れ歯には保険が適用されるものから、さまざまな特徴を持つ自費診療のものまで、多くの種類があります。
ここでは、医療費控除の対象となる入れ歯の種類や治療内容について、具体的な例を挙げて紹介します。
保険適用の入れ歯は基本的に控除対象
保険適用の入れ歯は、医療費控除の対象です。
プラスチック素材で作られる一般的な入れ歯で、噛む機能を取り戻すという明確な治療目的があるためです。
ただし、保険適用の入れ歯は比較的安価で作製できるため、入れ歯の費用単独で年間10万円の基準を超えるケースは少ないかもしれません。
その場合は、同じ年にかかった他の病気やケガの治療費、薬代、通院交通費などと合算して10万円を超えれば、医療費控除を申請できます。
金属床義歯やノンクラスプデンチャーなど自費入れ歯の扱い
自費診療の入れ歯も、機能回復が目的であれば医療費控除の対象となります。
自費の入れ歯は高額になることが多いため、医療費控除の恩恵を受けやすいといえるでしょう。
【対象となりうる自費入れ歯の例】
- 金属床義歯
- ノンクラスプデンチャー
- マグネットデンチャー
- シリコン義歯 など
また、金やポーセレンといった高価な材料を使用した場合でも、現在では一般的な治療材料と見なされており、控除の対象に含まれます。
審美目的の治療は対象
医療費控除で注意したいのは、治療の目的が容姿の美化、つまり審美性の向上のみである場合です。
このようなケースでは、医療費控除の対象外となります。
例えば、歯を白くするホワイトニングや、機能的に問題がない歯並びをさらに美しく見せるための矯正治療などが該当します。
入れ歯治療は基本的に機能回復が主目的のため、審美性を高める材料を使ったとしても、多くは控除の対象と認められます。
しかし、最終的な判断は税務署が行うため、治療前に歯科医師に機能回復を目的とした治療であるかを確認しておきましょう。
(参考:国税庁『医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例』)
医療費控除を受けるために必要な準備とは
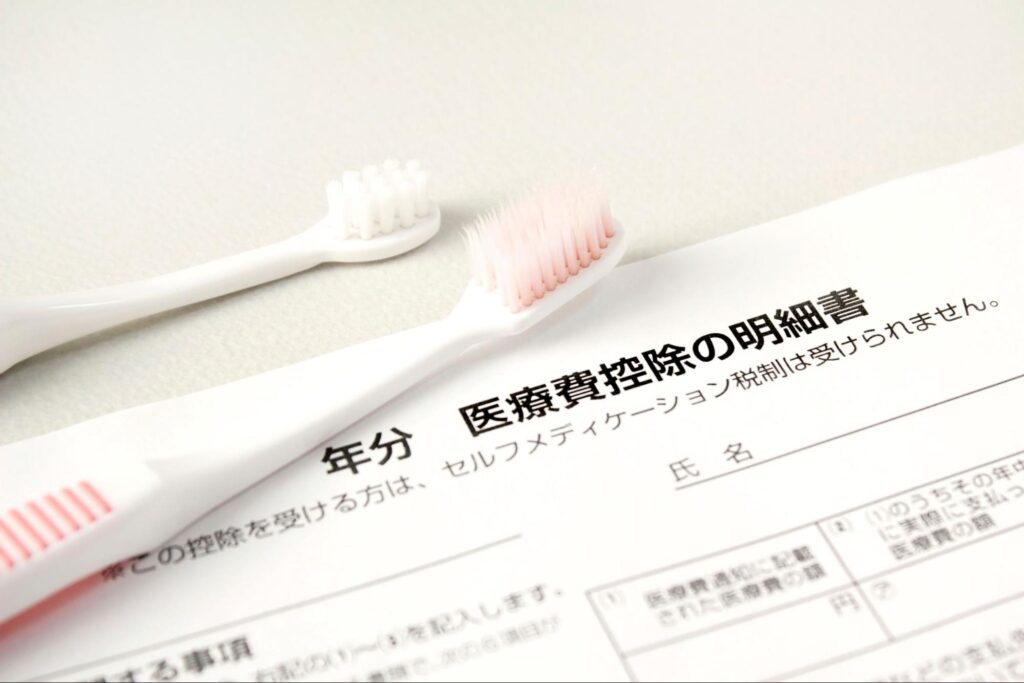
医療費控除は自動的に適用されるものではなく、ご自身で確定申告を通じて申請手続きを行う必要があります。
ここでは、医療費控除を受けるために必要な準備について、具体的なポイントを紹介します。
申請に必要な書類と保管しておくべきもの
医療費控除を申請するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
【主な必要書類】
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 給与所得の源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
以前は医療費の領収書の添付が必要でしたが、現在は医療費控除の明細書に内容を記入して提出します。
健康保険組合などから送られてくる医療費通知書を添付すれば、明細書の記入を一部省略できます。
なお、提出が不要になった医療費の領収書は、自宅で5年間保管する義務があるため、捨てずにまとめて保管しておきましょう。
歯科ローンやクレジット払いでも対象になるケース
入れ歯の治療費をデンタルローンやクレジットカードで支払った場合でも、医療費控除の対象となります。
ただし、申請するタイミングに注意が必要です。
| クレジットカード払いの場合 | カード会社から代金が引き落とされた日ではなく、歯科医院の窓口で支払い手続きをした日が属する年が控除対象 |
| デンタルローンの場合 | 信販会社が治療費を立て替えて歯科クリニックに支払った年が控除対象 |
なお、ローンの利息や手数料は医療費控除の対象外となるので注意しましょう。
デンタルローンを利用した場合は、領収書の代わりにローン契約書の写しなどを保管しておく必要があります。
交通費や薬代も忘れずに申請することが重要
医療費控除の対象となるのは、治療費だけではありません。
通院のために利用した公共交通機関(電車やバスなど)の交通費も合算して申告できます。領収書が出ない場合は、日付、利用した交通機関、区間、運賃などをメモに記録しておけば問題ありません。
ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となるため、注意が必要です。
また、歯科医師の処方に基づいて購入した医薬品の費用も控除の対象に含まれます。
これらの費用も忘れずに集計し、申告漏れがないようにしましょう。
(参考:国税庁『医療費控除の明細書』)
入れ歯の医療費控除に関するよくある質問

医療費控除の制度は少し複雑な面もあり、「自分の場合はどうなるのだろう?」と疑問に思う点も出てくるかもしれません。
ここでは、入れ歯の医療費控除に関してよく寄せられる質問と回答を紹介します。
入れ歯の医療費控除は家族全員でまとめて申請できる?
家族の医療費をまとめて申請することが可能です。
医療費控除は納税者本人だけでなく、『生計を一にする』配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。
『生計を一にする』とは、必ずしも同居している必要はありません。
例えば、単身赴任中の配偶者や、仕送りをしている地方の大学に通う子どもなどの医療費も対象になります。
入れ歯の医療費控除は所得によって異なる?
控除額の計算方法や還付される税額は所得によって異なります。
年間の総所得金額が200万円以上の方は支払った医療費から10万円を差し引きますが、200万円未満の方は総所得金額の5%を差し引きます。
また、最終的に還付される金額は、算出された控除額にその人の所得税率を掛け合わせて決まります。
所得税率は所得が高いほど高くなるため、同じ控除額であっても、所得が高い人ほど還付金は多くなる仕組みです。
入れ歯の医療費控除の申請はいつまでに行うべき?
医療費控除の申請は、確定申告の期間内に行います。
期間は、治療を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までです。
もし、この期間に申請を忘れてしまった場合でも、過去5年分までさかのぼって申告をすることが可能です。
まとめ
高額になりがちな入れ歯の費用ですが、機能回復を目的とした治療であれば、保険適用・自費診療を問わず医療費控除の対象となる可能性があります。
ご自身やご家族が1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得によっては総所得金額の5%)を超える場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
申請には、医療費の明細がわかるものや通院交通費の記録などが必要となるため、日頃から整理・保管しておくことが大切です。
下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、患者さま一人ひとりのお悩みやご不安に寄り添うことを第一に考えております。
費用に関するご不安や、ご自身の治療が医療費控除の対象になるかといったご質問にも丁寧にお答えします。
また、診療室はプライバシーに配慮した個室設計となっているため、周りを気にすることなくリラックスして治療していただけます。
入れ歯に関する疑問やご不安がございましたら、どうぞお気軽に下高井戸パール歯科クリニック・世田谷までご相談ください。
#入れ歯 #医療費控除



