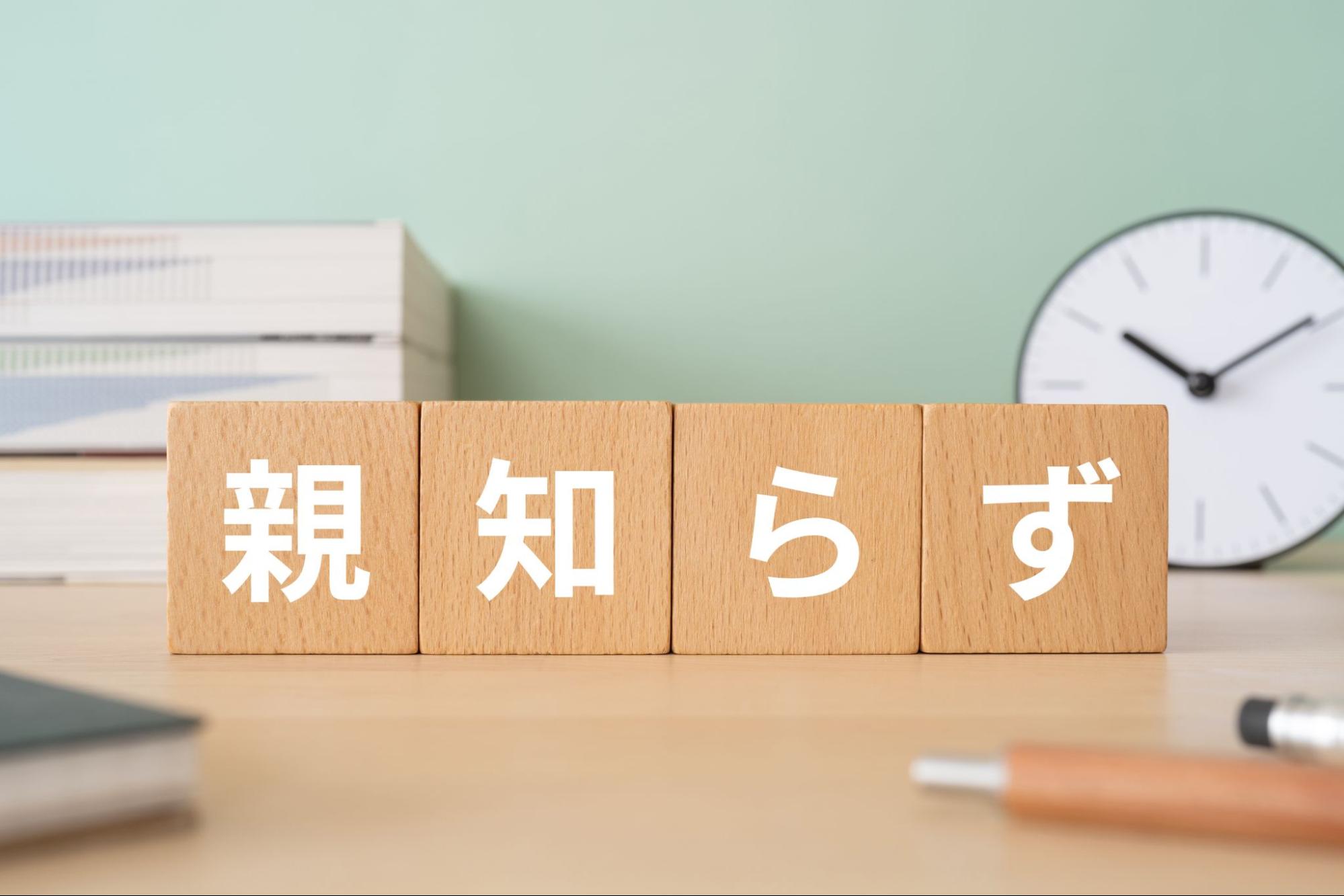
親知らずで痛みが出たり腫れたりして、抜歯を検討している方は多いのではないでしょうか。
しかし「親知らずは抜いた方がいい」という意見だけでなく「抜かなきゃよかった」という声もあり、判断に迷っている方はいませんか?
実は、親知らずを抜くべきかどうかは、生え方や口の中の状態によって大きく変わります。
そこでこの記事では、親知らずを抜くメリット・デメリット、抜歯が必要なケース、抜かなくてもいいケースを中心に解説していきます。
親知らずを抜く5つのメリット

親知らずを抜歯するメリットは以下のとおりです。
- 虫歯・歯周病リスクを大幅に減らせる
- 口臭予防になる
- 歯並びの悪化を防げる
- 智歯周囲炎を予防できる
- 歯磨きがしやすくなる
それぞれ見ていきましょう。
1.虫歯・歯周病リスクを大幅に減らせる
親知らずは口の一番奥にあるため歯ブラシが届きにくく、磨き残しが生じやすい場所です。
特に斜めに生えている場合は、歯と歯の間に汚れがたまりやすく、親知らずと隣り合う歯も虫歯になる可能性が高まります。
虫歯は自覚症状が乏しく、気づいた時には隣の第2大臼歯まで虫歯が進行していることは少なくありません。
また、親知らずの周りは歯周病の原因菌も繁殖しやすく、歯茎の炎症から始まって、最終的には顎の骨まで溶かしてしまうこともあります。
抜歯することで、こうしたリスクを軽減できます。
→虫歯を確かめる方法は?自宅でできる簡単チェックと歯科医院での検査を徹底解説
2.口臭予防になる
親知らず周辺の磨き残しは、細菌の温床となり口臭の原因になります。
特に歯の一部が歯茎に覆われている半埋伏智歯の場合、食べカスが入り込んで腐敗し、強い口臭を発生させることがあります。
どんなに丁寧に歯磨きをしても、ポケットの中まで清掃することは難しく、慢性的な口臭の原因となります。
しかし抜歯すれば、歯ブラシが届きやすくなり、口の中を清潔に保てるため、口臭の改善・予防につながります。
3.歯並びの悪化を防げる
親知らずが斜めや横向きに生えると、手前の歯を押して歯並びを乱す可能性があります。
特に下顎の親知らずは、真横に生えることが多く、継続的に手前の歯に圧力をかけ続けます。
圧力は前の歯にも伝わり、前歯の歯並びまで影響を与えることがあります。
せっかく矯正治療で整えた歯並びが、親知らずの影響で再び乱れてしまうケースも少なくありません。
早めの抜歯により、将来的な歯並びの悪化を防ぐことができます。
特に10代後半から20代前半の時期に抜歯することで、歯並びへの影響を抑えることが可能です。
4.智歯周囲炎を予防できる
智歯周囲炎は、親知らず周りの歯茎に起こる炎症のことです。
親知らずが完全に生えきらず、歯の一部が歯茎に覆われている状態で起こりやすく、そこに食べカスや細菌が入り込むことで発症します。
主な症状は、激しい痛みや腫れ、膿が出る、口が開きにくくなる、発熱、リンパ節の腫れなどです。
重症化すると、顔全体が腫れたり、喉の奥まで炎症が広がって呼吸困難を起こしたりする危険性もあります。
一度発症すると、原因となる親知らずが残っている限り、疲れやストレスで免疫力が低下した時に再発を繰り返します。
そのため、根本的に解決するには抜歯が必要です。
5.歯磨きがしやすくなる
親知らずは奥にあるうえ、横向きや斜めに生えているとなおさら磨きにくいものです。
しかし、抜歯すれば親知らずの清掃やデンタルフロス・歯間ブラシが使いやすくなり、他の歯のメンテナンスもしっかり行えるようになります。
親知らずを抜く4つのデメリットと対策

親知らずの抜歯にはメリットが多い一方で、デメリットもあります。
- 抜歯後の痛み・腫れ
- ドライソケットのリスク
- 将来の歯の治療で使えなくなる
- 神経損傷のリスク
しかし、対策することでデメリットを軽減することが可能です。
ここでは、主なデメリットとその対策方法について詳しく解説します。
1.抜歯後の痛み・腫れ
抜歯をすると、術後2〜3日は痛みや腫れが生じることが一般的です。
特に下顎の親知らずは骨が硬く、歯が深い位置にあることが多いため、上顎よりも腫れやすい傾向があります。
痛みや腫れを抑えるための対策は以下のとおりです。
- 処方された痛み止めを適切なタイミングで服用する
- 腫れや痛みがある場合は冷やしすぎに注意しつつ冷やす
- 激しい運動や飲酒、長時間の入浴は血行を良くして腫れを悪化させるため避ける
- 枕を高くして寝ることで、頭部への血流を減らす
仕事や学校がある方は、週末など休みが取れる時期に抜歯し、上記の対策に取り組んでみましょう。
2.ドライソケットのリスク
親知らずを抜いた後の穴には、血餅(けっぺい)という血のかたまりができ、傷口を保護しながら治っていきます。
ドライソケットとは、血餅がうまく作れなかったり、取れてしまったりして、抜歯した穴の骨が露出した状態のことです。
抜歯後の痛みは2〜3日で治るのが一般的ですが、ドライソケットになると抜歯後3〜4日してから激しい痛みが始まり、1週間以上続く場合があります。
発生は稀ですが、喫煙者で発生しやすい傾向があります。
ドライソケットを予防する対策は以下のとおりです。
- 抜歯後3日間は強いうがいを避ける
- 喫煙者は抜歯前後少なくとも1週間は禁煙を心がける
- 抜歯部位を舌で触ったり、吸ったりしない
- 抜歯当日は熱い食べ物や刺激物を避けて柔らかい食事を心がける
もしドライソケットになってしまった場合は、歯科医院で適切な処置を受けましょう。
3.将来の歯の治療で使えなくなる
まっすぐ生えていて大きな問題のない親知らずは、将来ほかの歯を失った際に移植したり、ブリッジの土台として活用したりできる可能性があります。
若い方の場合、親知らずの歯根膜(歯と骨をつなぐ組織)が健康であれば、他の部位に移植して機能させることも可能です。
また、親知らずの手前の第2大臼歯と呼ばれる歯を失った場合、親知らずを矯正治療で前方に移動させて、失った歯の代わりにすることもできます。
しかし一度歯を抜いてしまうと、こうした治療の選択肢がなくなってしまいます。
対策としては、抜歯が本当に必要かどうかを総合的に判断することが大切です。
たとえば、まっすぐ生えていて、きちんと磨ける親知らずであれば残す価値がありますが、トラブルを繰り返している親知らずは、将来的に移植に使える可能性よりも、現在のリスクの方が高いと考えられます。
歯科医師と相談し、メリットとデメリットを比較検討したうえで決めましょう。
4.神経損傷のリスク
下顎の親知らずは、下唇の感覚に関わる神経の近くに生えていることがあります。
抜歯の際に、この神経を傷つけてしまうと下唇にしびれが残ることがあります。
しびれが出るケースは稀ですが、親知らずの根っこが神経にくっついている場合は注意が必要です。
もし、しびれが出た場合は「唇を触っても感覚が鈍い」「ピリピリする」といった症状が現れます。
こうしたリスクを回避して抜歯するために、歯科医院では以下のような対策がとられます。
- CTで神経の位置を正確に把握
- 難しいケースは口腔外科の専門医が担当
- リスクが高い場合は大学病院を紹介
親知らずを抜くべき基準

親知らずを抜歯すべきかどうか迷っている方に向けて、抜歯を検討すべき具体的なケースを紹介します。
次のような症状や状態がある場合は、早めに歯科医院の受診をおすすめします。
腫れや痛みを繰り返している
親知らず周りの歯茎が何度も腫れたり、痛みが出たりする場合は、智歯周囲炎を繰り返している可能性が高いです。
一時的に抗生物質を飲んで症状が改善しても、根本的な原因が解決されない限り再発します。
繰り返すうちに、炎症が深部に広がり、顔全体が腫れたり、口が開かなくなったりする重篤な症状に発展することもあります。
炎症がある時に抜歯すると麻酔が効きにくく、術後の経過も悪くなる傾向があるため、症状が落ち着いている時期に抜歯を検討しましょう。
→親知らずの痛み止めの種類は?痛みが生じる原因と悪化を防ぐ方法も解説
親知らずや隣の歯が虫歯になっている
親知らずは歯ブラシが届きにくいため、虫歯になりやすい歯です。
親知らず自体が虫歯になるだけでなく、隣接する第2大臼歯との間や第2大臼歯の根元に虫歯ができることも多いです。
特に根元部分の虫歯は治療が難しく、最悪の場合、第2大臼歯も抜歯しなければならなくなることがあります。
親知らずが虫歯になっている場合、治療をしても再発リスクが高いため、抜歯を検討すべきです。
親知らずの生え方が悪い
親知らずが横向きや斜めに生えていて、手前の歯を押している場合は、歯並びが悪くなる原因となります。
特に下顎の親知らずが真横に生えている場合、継続的に前の歯を押し続けるため、時間の経過とともに歯並びが悪化していきます。
前歯が重なり合って歯並びが乱れると、見た目の問題だけでなく、歯磨きがしにくくなり、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
口が開きにくい・顎が痛い
親知らずが原因で噛み合わせのバランスが崩れると、顎関節に負担がかかり、さまざまな症状が現れることがあります。
多くの場合、親知らずの痛みを避けるために無意識に片側だけで噛むようになってしまいます。
片側の顎関節や筋肉を使いすぎることで、顎関節症を発症し、口を開けると音がする、大きく開けられない、顎が痛いといった症状が出てくるのです。
さらに、親知らずが炎症を起こすと、痛みで口を開けにくくなることもあります。
炎症を繰り返すうちに顎の筋肉が硬くなり、慢性的に口が開きにくい状態になってしまうため、早めの対処が必要です。
頬を噛んでしまう
親知らずが頬側に傾いて生えている場合、頬の内側を噛んでしまうことがあります。
食事中に何度も同じ場所を噛んでしまい、その部分が腫れて、また噛んでしまうという悪循環に陥りやすくなります。
慢性的なダメージは、潰瘍を起こす可能性もあるため注意が必要です。
頬を噛む癖がついてしまう前に、原因となる親知らずの抜歯を検討することをおすすめします。
口臭が気になる
親知らず周りに汚れがたまると、細菌の繁殖による口臭の原因となります。
特に、親知らずが半分だけ生えていて、歯茎に一部埋まっている状態では、歯と歯茎の間に深いポケットができます。
ポケットに入り込んだ食べカスや細菌は、歯磨きで取り除くのが難しく、最終的に腐敗して強い臭いを発生させてしまうのです。
また、親知らず周りで歯周病が進行すると、膿が出ることもあり、これも強い口臭の原因となります。
親知らずの抜歯についてのよくある質問

親知らずの抜歯についてのよくある質問をまとめました。
Q1:親知らずは必ず抜かなければいけませんか?
いいえ、必ずしも抜く必要はありません。
まっすぐ生えていて、上下でしっかり噛み合い、歯磨きも問題なくできる場合は残しておくことができます。
ただし、虫歯や歯周病のリスクが高い場合、隣の歯に悪影響を与えている場合、繰り返し腫れや痛みが出る場合は抜歯を検討しましょう。
定期的に歯科検診で状態を確認し、歯科医師と相談しながら判断することが大切です。
Q2:親知らずを抜くのに最適な年齢はありますか?
親知らずの抜歯は、10代後半から20代前半が適していると言われています。
この時期は骨がまだ柔らかく、歯根も完全に形成されていないため、抜歯が比較的簡単で、術後の回復も早いのが特徴です。
ただし、問題がある親知らずは年齢に関係なく早めに対処することが大切です。
30代以降でも抜歯は可能ですが、術後の経過を注意して追う必要があります。
Q3:親知らずが原因で起こる症状にはどんなものがありますか?
親知らずが原因で起こる症状には、親知らず周辺の痛みや腫れ、歯茎の炎症、口臭、隣の歯の虫歯、歯並びの悪化、顎関節症、頭痛や肩こりなどがあります。
また、親知らずの周りに細菌が繁殖すると、顔が腫れたり、口が開きにくくなったりすることもあります。
このような症状がある場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。
まとめ
親知らずを抜くかどうかは、メリット・デメリットを総合的に判断することが大切です。
虫歯や歯周病のリスク軽減、口臭予防、歯並びの維持など、親知らずの抜歯には多くのメリットがありますが、術後の痛みや将来の治療選択肢が減るなどのデメリットもあります。
親知らずが気になり、抜歯するかどうか悩んでいる場合は、早めに歯科医院で相談しましょう。
下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、日本口腔外科専門医による専門的な親知らずの診察・治療を行っています。
精密な検査診断も可能で、難症例にも対応していますので、まずは一度ご相談ください。
#親知らず #親知らず抜歯



